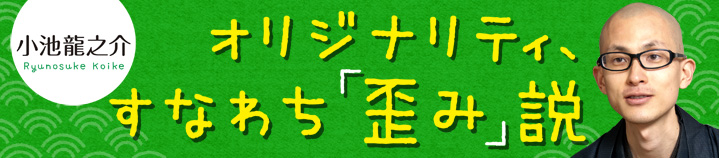第2回 ネガティブな感情は、こうして生まれる
前回、私たちは現実世界の書き換えを行なってしまっていることを述べました。
さらに、私たちの「人に対する評価」というのも、おおむね「書き換え」によって生じているものにすぎません。たとえば、ある家庭の奥様とその家にきた訪問販売員について考えてみましょう。
奥さんからすると、販売員は、
「あぁ、奥様はお美しくていらっしゃいますねー」
「今日も素敵な髪型でいらっしゃって……」
と会うたびに毎回ほめてくれる。どこかで「それはお世辞なんじゃないかしら」と思いつつも、毎回毎回すごく一生懸命ほめてくれれば、「この人はポジティブなことをいつも言ってくれるから、良い人ね」というような判断が生じるでしょう。
でも、前回お話ししたオーストラリアの気温と同じように、その販売員自身に「良い人」という属性があるわけではありません。営業という目的のために、良さそうなことを話しただけだったり、そのために優しそうな笑顔だったりするだけ、かもしれないのです。けれども、そういったものをもとに、「この人は良い人だ」「この人の言葉は良い言葉だ」というふうに、物事を頭の中で書き加えてしまう。結果として、「良い」という幻の判断が生まれるのですね。
ただその「良い」というのは、自分の勝手で脳内において書き加えた事柄ですので、実体はなく、永続するとは限らないわけです。
実際のところ、その販売員がそのようにほめるのをやめて、一生懸命何かを売りつけようとしてきた場合は、「あんなにいい人だと思っていたのに、こんなに無理矢理売りつけようとするなんて、ひどい人だ」というふうに判断がコロッと変わるかもしれません。
厄介なことに、その反対方向に判断が変わったからといって、「じゃあ、さっきまで間違っていたのが今度は正しい判断になったのか」というと、それも違います。その人に、「ひどい人」とか「よこしまな人」という属性が実体として与えられるわけではないのです。
前に勝手に「いい人だ」と自分が思いこんでいた、その思いこみが覆された分だけ、その反動で余計に強く、「悪い人だ」という判断が自分の頭の中で、書き加えられているだけだったりします。
元が良ければ良いほど、そのあとに生じるネガティブな感情は、強くなりがちなのです。
それは現実を「ただそのようである」と置いておかずに「書き換えた」から起こることです。「良いものだ」「イヤなものだ」などと書き換えるから、ネガティブな感情が生じやすくなるのです。
これこそが、「書き換え」に注意を払うことの理由と言えましょう。
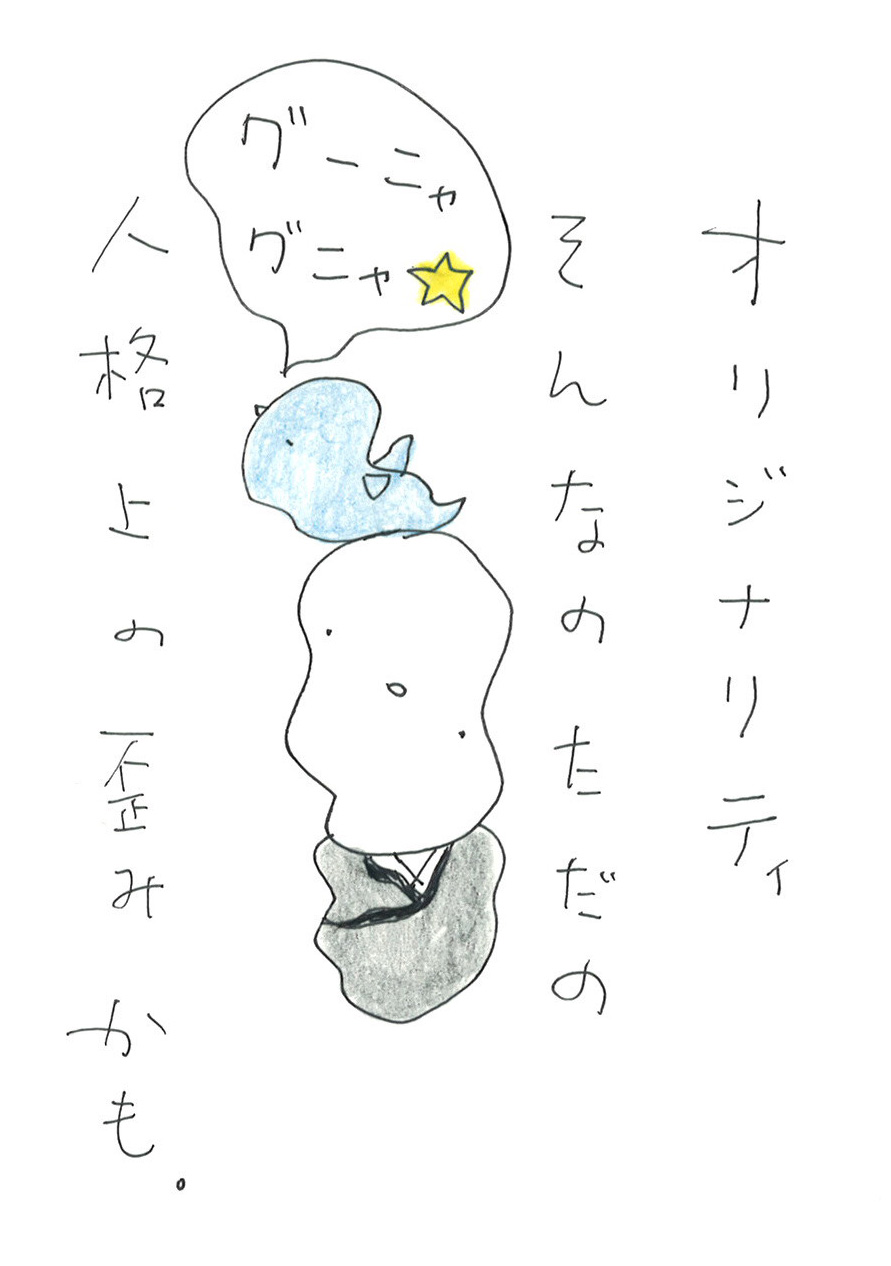
さらに、私たちの「人に対する評価」というのも、おおむね「書き換え」によって生じているものにすぎません。たとえば、ある家庭の奥様とその家にきた訪問販売員について考えてみましょう。
奥さんからすると、販売員は、
「あぁ、奥様はお美しくていらっしゃいますねー」
「今日も素敵な髪型でいらっしゃって……」
と会うたびに毎回ほめてくれる。どこかで「それはお世辞なんじゃないかしら」と思いつつも、毎回毎回すごく一生懸命ほめてくれれば、「この人はポジティブなことをいつも言ってくれるから、良い人ね」というような判断が生じるでしょう。
でも、前回お話ししたオーストラリアの気温と同じように、その販売員自身に「良い人」という属性があるわけではありません。営業という目的のために、良さそうなことを話しただけだったり、そのために優しそうな笑顔だったりするだけ、かもしれないのです。けれども、そういったものをもとに、「この人は良い人だ」「この人の言葉は良い言葉だ」というふうに、物事を頭の中で書き加えてしまう。結果として、「良い」という幻の判断が生まれるのですね。
ただその「良い」というのは、自分の勝手で脳内において書き加えた事柄ですので、実体はなく、永続するとは限らないわけです。
実際のところ、その販売員がそのようにほめるのをやめて、一生懸命何かを売りつけようとしてきた場合は、「あんなにいい人だと思っていたのに、こんなに無理矢理売りつけようとするなんて、ひどい人だ」というふうに判断がコロッと変わるかもしれません。
厄介なことに、その反対方向に判断が変わったからといって、「じゃあ、さっきまで間違っていたのが今度は正しい判断になったのか」というと、それも違います。その人に、「ひどい人」とか「よこしまな人」という属性が実体として与えられるわけではないのです。
前に勝手に「いい人だ」と自分が思いこんでいた、その思いこみが覆された分だけ、その反動で余計に強く、「悪い人だ」という判断が自分の頭の中で、書き加えられているだけだったりします。
元が良ければ良いほど、そのあとに生じるネガティブな感情は、強くなりがちなのです。
それは現実を「ただそのようである」と置いておかずに「書き換えた」から起こることです。「良いものだ」「イヤなものだ」などと書き換えるから、ネガティブな感情が生じやすくなるのです。
これこそが、「書き換え」に注意を払うことの理由と言えましょう。
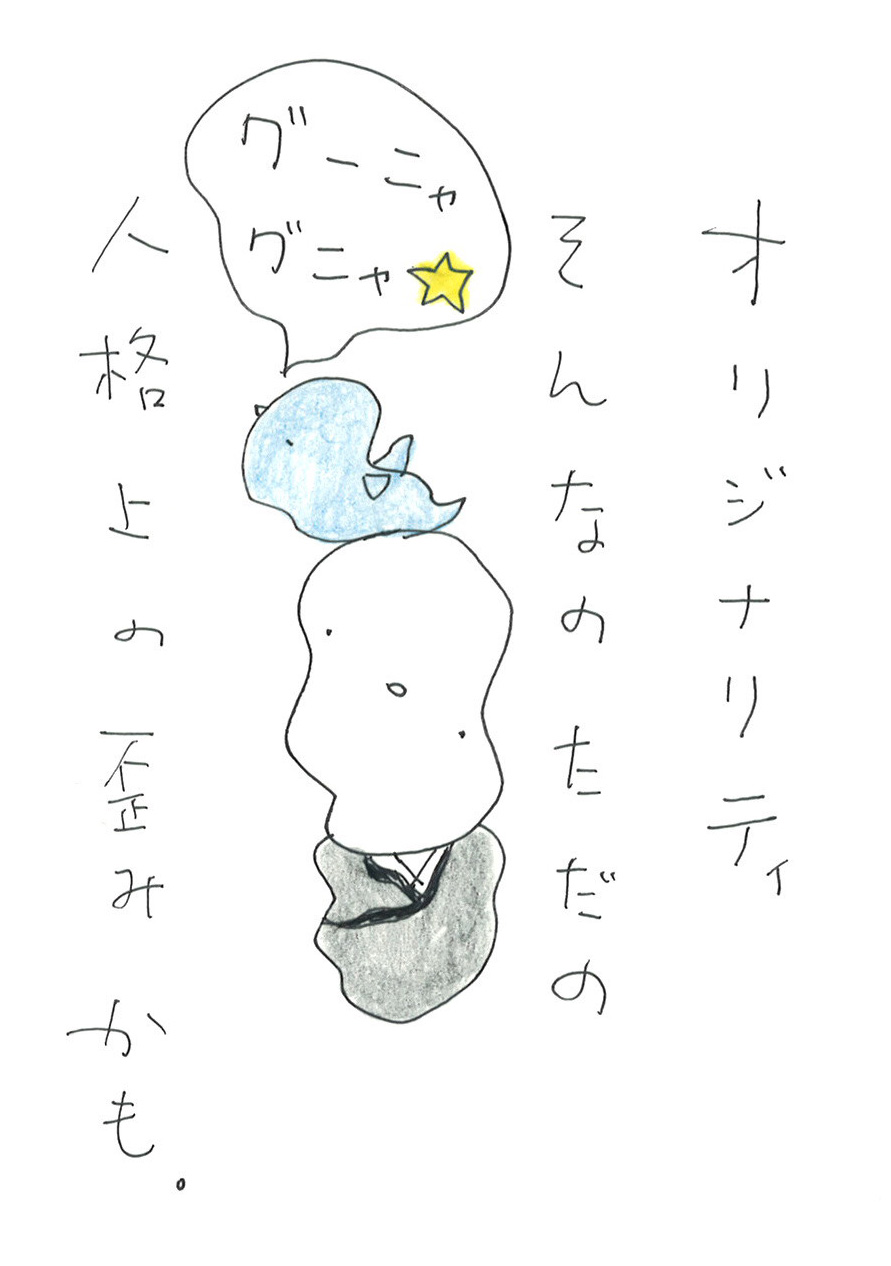
著者プロフィール
小池龍之介(こいけりゅうのすけ)
1978年生まれ。山口県出身。東京大学教養学部卒業。
月読寺(神奈川県鎌倉市)住職、正現寺(山口県山口市)住職、ウェブサイト「家出空間」主宰。僧名は龍照。
住職としての仕事と自身の修行のかたわら、一般向け坐禅指導も行なう。
著書に『読むうちに悩みが空っぽになる「人生相談」』(三笠書房《王様文庫》)、『沈黙入門』『もう、怒らない』(ともに幻冬舎)、 『考えない練習』『苦しまない練習』(ともに小学館)、 『超訳 ブッダの言葉』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、 『平常心のレッスン』(朝日新聞出版社)、『しない生活』(角川書店)などがある。
1978年生まれ。山口県出身。東京大学教養学部卒業。
月読寺(神奈川県鎌倉市)住職、正現寺(山口県山口市)住職、ウェブサイト「家出空間」主宰。僧名は龍照。
住職としての仕事と自身の修行のかたわら、一般向け坐禅指導も行なう。
著書に『読むうちに悩みが空っぽになる「人生相談」』(三笠書房《王様文庫》)、『沈黙入門』『もう、怒らない』(ともに幻冬舎)、 『考えない練習』『苦しまない練習』(ともに小学館)、 『超訳 ブッダの言葉』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、 『平常心のレッスン』(朝日新聞出版社)、『しない生活』(角川書店)などがある。
バックナンバー
- 2014年10月03日 第1回 物事そのものは「良く」も「悪く」もない
- 2014年11月26日 第2回 ネガティブな感情は、こうして生まれる
- 2014年12月25日 第3回 行き過ぎた「オリジナリティ」が争いのもと
- 2015年01月16日 第4回 「個性」、という苦しみ
- 2015年02月20日 第5回 瞑想とは、ラクに生きるレッスン