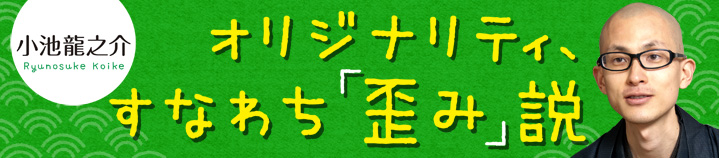第1回 物事そのものは「良く」も「悪く」もない
昨今、「禅」や「瞑想」に少し、注目が集まっているようです。
多くの方はご存じかもしれませんが、「瞑想」というものは、ただ目を閉じて座っているということではありません。
では、「瞑想」というのは、どういうものなのでしょうか。
本コラムでは、
「そもそも瞑想とは、一体何かなぁ」
「瞑想中はどういうふうに心や体が動き、どんな作業をやっているのかなぁ」
ということを、5回にわたって見ていきたいと思います。
私は今、鎌倉や山口で定期的に瞑想のレッスンを行なっていますが、始める前に皆さんに、
「執着を手放していくことにしましょう」
「呼吸を通じて自分の体と心を整えましょう」
などと申します。それらの根幹の根幹にあるのは、つまり瞑想とは、「物事をありのままに受け止めることに尽きる」ということです。
「物事をありのままに受け止める」とは、「物事を受け止めたあとに、私たちの主観によって、その受け止めたものを書き換えない」ということ。
「書き換える」というのは、たとえば気温が低い日に「寒いなぁ」と思うだけではなくて、「寒いからイヤだなあ」など、天候によって与えられた情報を自分の判断によって、「それはイヤなものだ」と頭の中でとらえ直すということです。
この「書き換える」ということについて、もう少し考えてみましょう。
「寒いのはイヤだなぁ」というのが前提にあれば、暖かくなると、「あ、うれしい」という気持ちが生じます。たとえば日本が寒い季節にオーストラリアに行くと暖かいはずです。「寒いのがイヤだなぁ」と思う人は、飛行機に乗ってオーストラリアに降り立ったときには、「あー、日本は寒かったけどここは暖かい、良かったー」と思うでしょう。
でも一方で、オーストラリアにもともと住んでいる人にとっては、別段「良かったー」と思うことはありません。
つまり、オーストラリアのその季節そのものに「良い」という要素とか、「暖かくて素敵」という要素が含まれているわけではないわけですね。
あるのは「暖かいという現実」だけで、その「現実」に対して、「良かった」「悪かった」と私たちは頭の中で判断し、情報を書き換えているのです。
さらに、その書き換えられた情報から連想していくと、たとえばオーストラリアで、
「あー、暖かくて素敵だから今すぐここに住もう」
「寒くなくて良いから、引っ越してこよう」
など、いろいろなことを思うかもしれません。もちろん、時としてそういう判断が、実際に良い結果をもたらすこともあるでしょう。
しかし、ただ一時的に感情がうわついて、連鎖的にどんどん現実を書き換えていったときに、「現実のありのまま」とは随分違ったところに頭の中がいきつくことがあるのです。
そこからさらに書き換えが進んだ結果、とんでもない判断になってしまうことさえあります。
次回は、さらに「書き換え」の例をご紹介しながら、なぜ仏教では「書き換えをしないことにしよう」ということを求めるのか、考えてまいりましょう。
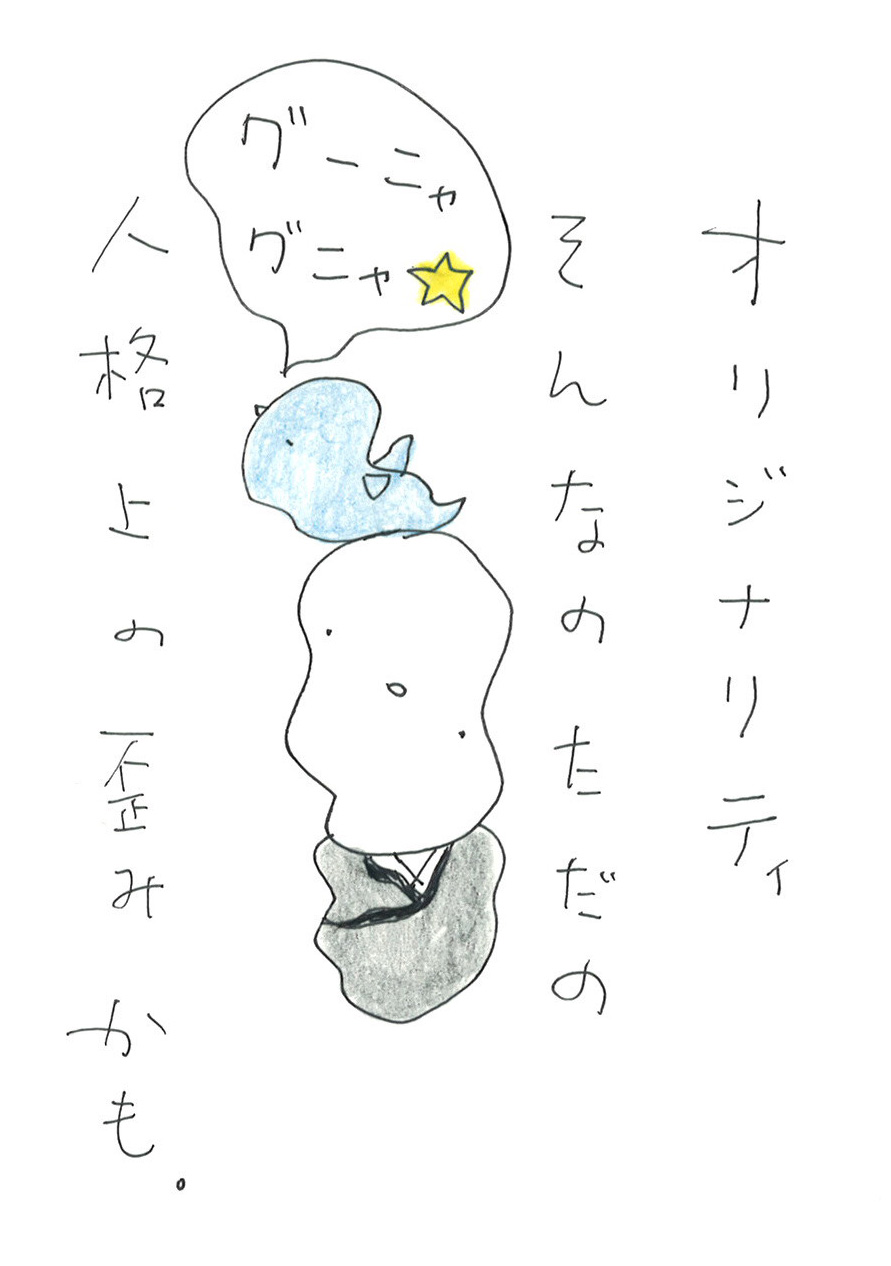
多くの方はご存じかもしれませんが、「瞑想」というものは、ただ目を閉じて座っているということではありません。
では、「瞑想」というのは、どういうものなのでしょうか。
本コラムでは、
「そもそも瞑想とは、一体何かなぁ」
「瞑想中はどういうふうに心や体が動き、どんな作業をやっているのかなぁ」
ということを、5回にわたって見ていきたいと思います。
私は今、鎌倉や山口で定期的に瞑想のレッスンを行なっていますが、始める前に皆さんに、
「執着を手放していくことにしましょう」
「呼吸を通じて自分の体と心を整えましょう」
などと申します。それらの根幹の根幹にあるのは、つまり瞑想とは、「物事をありのままに受け止めることに尽きる」ということです。
「物事をありのままに受け止める」とは、「物事を受け止めたあとに、私たちの主観によって、その受け止めたものを書き換えない」ということ。
「書き換える」というのは、たとえば気温が低い日に「寒いなぁ」と思うだけではなくて、「寒いからイヤだなあ」など、天候によって与えられた情報を自分の判断によって、「それはイヤなものだ」と頭の中でとらえ直すということです。
この「書き換える」ということについて、もう少し考えてみましょう。
「寒いのはイヤだなぁ」というのが前提にあれば、暖かくなると、「あ、うれしい」という気持ちが生じます。たとえば日本が寒い季節にオーストラリアに行くと暖かいはずです。「寒いのがイヤだなぁ」と思う人は、飛行機に乗ってオーストラリアに降り立ったときには、「あー、日本は寒かったけどここは暖かい、良かったー」と思うでしょう。
でも一方で、オーストラリアにもともと住んでいる人にとっては、別段「良かったー」と思うことはありません。
つまり、オーストラリアのその季節そのものに「良い」という要素とか、「暖かくて素敵」という要素が含まれているわけではないわけですね。
あるのは「暖かいという現実」だけで、その「現実」に対して、「良かった」「悪かった」と私たちは頭の中で判断し、情報を書き換えているのです。
さらに、その書き換えられた情報から連想していくと、たとえばオーストラリアで、
「あー、暖かくて素敵だから今すぐここに住もう」
「寒くなくて良いから、引っ越してこよう」
など、いろいろなことを思うかもしれません。もちろん、時としてそういう判断が、実際に良い結果をもたらすこともあるでしょう。
しかし、ただ一時的に感情がうわついて、連鎖的にどんどん現実を書き換えていったときに、「現実のありのまま」とは随分違ったところに頭の中がいきつくことがあるのです。
そこからさらに書き換えが進んだ結果、とんでもない判断になってしまうことさえあります。
次回は、さらに「書き換え」の例をご紹介しながら、なぜ仏教では「書き換えをしないことにしよう」ということを求めるのか、考えてまいりましょう。
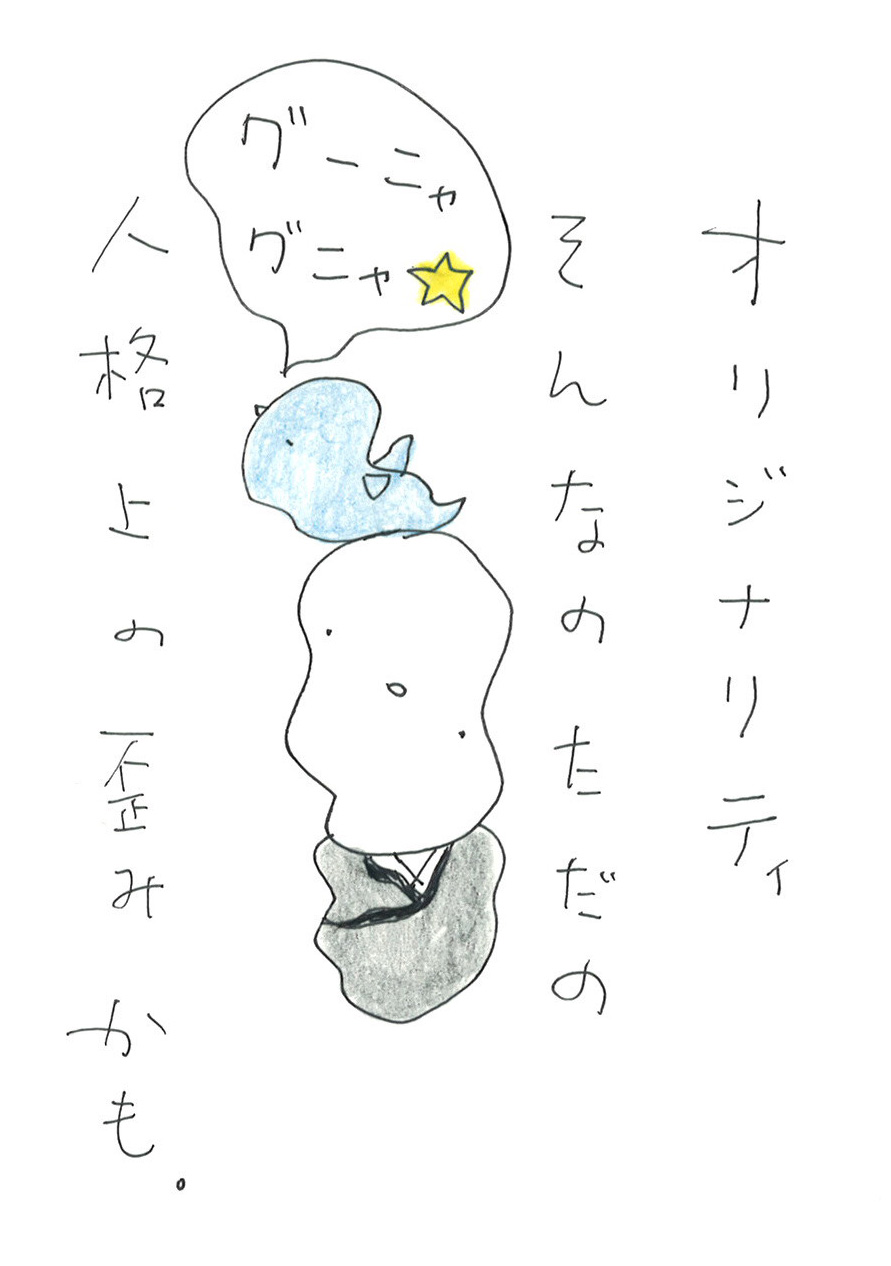
著者プロフィール
小池龍之介(こいけりゅうのすけ)
1978年生まれ。山口県出身。東京大学教養学部卒業。
月読寺(神奈川県鎌倉市)住職、正現寺(山口県山口市)住職、ウェブサイト「家出空間」主宰。僧名は龍照。
住職としての仕事と自身の修行のかたわら、一般向け坐禅指導も行なう。
著書に『読むうちに悩みが空っぽになる「人生相談」』(三笠書房《王様文庫》)、『沈黙入門』『もう、怒らない』(ともに幻冬舎)、 『考えない練習』『苦しまない練習』(ともに小学館)、 『超訳 ブッダの言葉』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、 『平常心のレッスン』(朝日新聞出版社)、『しない生活』(角川書店)などがある。
1978年生まれ。山口県出身。東京大学教養学部卒業。
月読寺(神奈川県鎌倉市)住職、正現寺(山口県山口市)住職、ウェブサイト「家出空間」主宰。僧名は龍照。
住職としての仕事と自身の修行のかたわら、一般向け坐禅指導も行なう。
著書に『読むうちに悩みが空っぽになる「人生相談」』(三笠書房《王様文庫》)、『沈黙入門』『もう、怒らない』(ともに幻冬舎)、 『考えない練習』『苦しまない練習』(ともに小学館)、 『超訳 ブッダの言葉』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、 『平常心のレッスン』(朝日新聞出版社)、『しない生活』(角川書店)などがある。
バックナンバー
- 2014年10月03日 第1回 物事そのものは「良く」も「悪く」もない
- 2014年11月26日 第2回 ネガティブな感情は、こうして生まれる
- 2014年12月25日 第3回 行き過ぎた「オリジナリティ」が争いのもと
- 2015年01月16日 第4回 「個性」、という苦しみ
- 2015年02月20日 第5回 瞑想とは、ラクに生きるレッスン